ローマでの生活、しかし基本的には日々仕事のみであった。
休みは週に一回貰い、その時は電車などに乗って買い物に行ったり、近場でのんびりと過ごした。
仕事ですでにローマの多くの観光地に行けていた事はとても大きかったと思う。
その分逆に休日にやる事がなくなったが^^;
目次
ある日の朝
ある日の朝、僕はいつものように出勤し、コロッセオにいた。
年が明け、一月の下旬。肌寒いが青空の澄み切った気持ちの良い朝だった。
僕がここにやってきてからちょうど1ヶ月が経った頃でもあった。
その日も変わらずに、新たな一日を迎えようとしていた。
と、突然、僕の携帯電話が鳴った。それは加藤さんからだった。
朝早くから珍しい、どうしたんだろう?
電話にでると、加藤さんはこちらの返事を待たずに喋り出した。
『一柳さんが倒れた。病院に行ってから向かう。それまで一人でやっててくれ』
突然の電話に驚いたが、何かを聞き返す余裕はなく、とりあえず大事に僕はただうなずくだけだった。
加藤さんはお昼すぎになってようやく現場に現れた。
そこには浮かない顔の彼がいた。
事情を聞くと、その重い口を開いてくれた。
それによると、今朝、シャワーを浴びていた一柳さんは浴室で倒れたらしい。
幸いにも同居人がすぐにそれを発見し、救急車へ通報した。そして近くにある大きな病院へと運ばれ処置や検査が施された。
しかし意識は戻らずに現在は集中治療室に入っているとのことだった。
僕は驚きのあまり声が出なかった。
なんて事だ…。
その日一日は僕らは重い心で過ごしたのだった。
検査結果と病状
その夜、仕事が終わり、僕らは病院へと駆けつけた。
すでに昼間から別のスタッフがずっと病院の待合室で待機していて、その後の検査結果を教えてくれた。
それによると、状況は僕らが思っていた以上に深刻だった。
『脳溢血』
これが一柳さんの病状だった。
これは脳の血管が破裂し、脳の神経を圧迫して起きるらしい。
このまま昏睡状態が続き、意識が戻らないと非常に危険らしい。
また、一柳さんは集中治療室にいる為に面会謝絶。僕らは待合室で神に祈る他なかった。
過ぎ去る日々
次の日からも僕らは日々の業務をこなした。
こんな状況だからこそ頑張らないといけない。
一柳さんに心配かけまいと僕らは必死になってやった。
彼が無事に戻って来た時に喜んでもらいたい。そんな思いだった。
しかしその後も、二日、三日、四日と経っても彼の意識が戻ることはなかった。
僕らも毎日日替わりで病院に付き、待合室で先生から入る新しい情報を待った。
しかしそこに喜ばしい情報はなく、無情にも時間だけが過ぎていくのであった。
僕らスタッフの顔にも疲労の色が浮かんでいた。
誰もこの先のことなんて分からないし、こんなのはただの一時の事で、またすぐに一柳さんはいつものように笑いながら飄々と僕らの前にその姿を表すのだろうと思っていた。
しかし、その願いは儚くも崩れ去った。
倒れてからちょうど七日目の事だった。
その日の明け方早く、彼は静かに息を引き取ったのだった。
それはあまりにも突然のことだった。
残された者達
一体何が起きているんだろう?
始めは今の状況がよく理解できなかった。
が、それはどうやら現実に起きた事らしかった。
しかし時として人生とは無常で、僕らは悲しみに浸る間もなく、そして会社は大パニックへと陥った。
従業員10名の小さな会社では、その全ての経営が社長のワンマン体制だった。
全ての取引やプロジェクト、支払いやアポイントメントなどその他諸々、これらはいったいどうなっているのだろう。
そんな指揮官を失った船では、このままでは沈没するのは時間の問題だった。
残された僕らは早急に決断をしなければいけなかった。
会社をこのまま畳むのか、誰かが業務を引き継ぎ新体制で再スタートさせるのかを。
一柳さんにはパートナーや子供はいない。若い頃にこの地にやって来て以来ずっと独り身であったのだ。
加藤さんや、ほか会社の中で一柳さんの右腕としてずっとやって来た女性はいたが、会社を引き継ぐというのはそう簡単なことではない。
僕らは決断を強いられた。
悲しみとその人柄
一柳さんの訃報は瞬く間に関係者の間を駆け巡った。
会社運営ががたがたの間も、お客さんは来る。契約を持っているところもあり、そこに迷惑をかけるわけにはいかない。
加藤さんや上層部の人間が会社運営について話し合っている間も、僕は自分にできることを一生懸命にこなした。
コロッセオに立つと、訪れるグループのガイドさん達、一柳さんは当然ながらその全員と面識や交流があった。
突然の訃報に皆、驚きの表情であり、僕は事の次第を会社代表として皆さんに伝えた。
その悲しみや痛み、嘆き、それらは当然深いもので、僕が彼を知る以上に長い付き合いのある方々。それは、彼がこの地で20年という時間を過ごして来た重みだった。
ガイドさんの中には、写真撮影や僕らを面倒臭いと避けていた人もいたが、一柳さんの訃報を知ると大きな涙を流し、これからこの会社を応援する為に写真を積極的に撮るね、と言ってくれる者さえいた。
訪れる添乗員さんの中にも、彼と親しい人がよくいて、突然の事に衝撃を受けていた。
僕は一柳さんの影響力の大きさを改めてここで知ったのであった。
恩の返し方
一柳さんの葬儀は早急に行われた。
日本からご家族の方が来て、病院に併設されていた教会の礼拝堂のような場で行われた。
そこには多くの友人や知人、仕事関係者らが来てお花を供えられた。
そして肝心の会社の方は長い話し合いの末、一柳さんの右腕として15年間共にしてきた女性と、それを支える加藤さんという形で会社を継続することが決まった。
それは、一柳さんの夢や意思を叶えたい、また彼の人柄や恩を次世代に引き継ぎたいという思いからだった。
それで僕はというと、僕もこの時大いに悩んだのである。
僕は旅人だ。この地にずっと留まるつもりはなかった。一柳さんが倒れる前にも、僕はちょうどその事で悩んでいたのだった。
一柳さんは僕を信頼し、この地にずっと留まって欲しい事をよく言っていた。
夢を語り、会社を大きくし、僕もそこで色々な事にチャレンジしないかとたくさんの夢を語ってくれた。
しかし同時に僕は世界を見たかった。まだまだ道のりの途中でそれを諦めたくはなかった。
いわばそれは僕の夢だ。
お金が尽き困っていた僕を救ってくれ、大きなチャンスを与えてくれた事には感謝してもしきれない。
そして当初は、とりあえず1ヶ月間だけでもやってみよう、というところから始まった。
その後の事はまたその時に決めればいい、というものであった。
そんな感じで僕もいつか出てしまうという後ろめたさ無くいれたのであった。
しかしローマでの仕事や滞在が順調に行き、信頼を得て安定しにいくにつれて、僕は一種の焦りのようなものも生まれてきていた。
このままここから出られなくなってしまうのではないだろうか、という…。
その事について、一柳さんとしっかりと話し合いたい。
そんな矢先に起きた出来事だったのであった。
しかし、この状況下で去っては、一柳さんから受けた御恩をあだで返すようなものだ。
加藤さんらの覚悟と決断。
僕もそれに応える形で、決めた。
会社が一通り落ち着くまでの期間、僕もみんなの為に、そして何より一柳さんの為に残る、と。
御縁の成すもの
一柳さんは、若い頃に夢を求めて単身ヨーロッパにやってきて、この会社を立ち上げた。
多くの苦労を伴ったらしいが、その苦労や愚痴を一柳さんが僕らに言うことは決してなかった。
僕は周りの古いスタッフから端々にさまざまなストーリーを聞いていた。
騙されたり、逃げられたりするというのは何度もあったようだ。また、後回しにされたり、要望を聞いてもらえなかったり、異国の地で仕事をすることの大変さは山のようにあったようだ。
またそれは日本人同士の中でもあったようだ。日本人でもこちらに来ている人は、訳アリの人や、癖がある人も多い。
一柳さんは、それでも信じ続けた。
『人は誰でも輝く原石だ。磨けば絶対に輝く。だから僕は信じる』と。
それは、初めて出逢った時、僕にも言ってくれた言葉だった。
いくら騙されても、いくら裏切られても、彼は最後の最後まで自分のその信念を貫き通し人を信じ続けた。
だって、だからこそこんな中途半端な僕でも信じてくれたし、チャンスを与えてくれた。そしてなによりも、僕こそが、彼の人生の中で最後に出逢った人物だったのだから。
彼はその人生で、自分にぶれる事なく人を信じ続けた。
僕はそう思うと、悼まれて仕方がなくなった。
–人との出逢いで運命が変わる–
その後、僕は半年間この地に留まった。
そこで懸命に仕事をこなしたのだった。
ここを出る時は後ろ髪を引かれる思いだったが、情に流されこれ以上この地で足踏みをし、自分自身を見失うようでは本末転倒だと思った。
今なら一柳さんは何と言うだろうか?
きっと、いつも口癖のように言っていたこの言葉でこう言うだろう。
『自分が与えられる付加価値を探せ』って。
僕は、世界を見たい!そしてそこから自分の使命を見つけたい。
この出来事が僕とイタリアとの出合いだった。
一柳さんと出逢った事により僕の運命が変わったのだった。
『人との出逢いで運命が変わる』
それを肌で実感した。
これは、その後の僕の人生の大きな岐路と、この時はまだ知る由も無かったが。
そしてこの時から、僕は何か大きな運命という大河の流れの渦中に入ったことを感じた。
この後、旅はいよいよアフリカへと突入するのだった。
–イタリア出合い編・終わり–
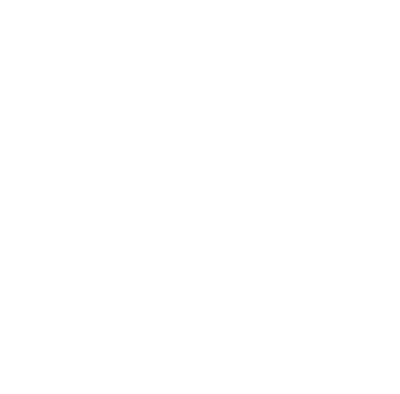 World Performing Blog!
World Performing Blog! 

