次の日から僕の一日の大半は、この世界遺産コロッセオの前で過ごすことが日課となった。
ついこの間までの自由な旅人生活からは一変したが、しかし、この古代建築を日々見上げながら、また世界中からの観光客が押し寄せるこの場所で時間を過ごすのも悪くなかった。
日々、感覚や感性が変化していく感じがあった。
目次
コロッセオと写真営業
上司である加藤さんが写真撮影と営業の一連の動きを教えてくれたが、それは思っている以上に簡単なことではなかった。
まず、コロッセオに団体客が着くと、遠巻きからその姿を確認できる。
200mほどの距離か。その時点で、まず欧米人かアジア人かが判断できる。
アジア人であった場合、日本人と紛らわしいのは韓国人と中国人だ。
しかし加藤さんや、一緒にやっているイタリア人のカメラマンたちは一瞬で判断できた。
「あれは日本人だ、行くぞ!」とすぐに反応できたり、僕が日本人ぽい人らを見つけて行こうとすると「あれは違う、ほっとけ」なんて具合に。
観光客はカモ?!
また他にも、ここには観光客目当てに色々な人たちが集まってきていた。
僕らの近くにいつもいたあるイタリア人は、サッカー観戦の個人ツアーをやっていて、彼も日本人観光客狙いだった。
僕らが写真を撮っている側で添乗員さんに話しかけ、グループ内で誰かオプショナルツアーでサッカー観戦に行きたい人がいないかと集っていた。
また、昔日本でも流行ったイタリアの伝統工芸品カメオの店の営業の人もいた。その彼もまた日本人狙いで、添乗員さんにうまく話しかけて彼の勤めるお土産屋さんへとグループを連れて行こうとした。
他にも日替わりで、何かの営業の人が来ていたりした。いづれも日本人狙いだったので、自然と僕らのところに集まってくる訳だった。
そんなんで日中、日本人グループが来ない暇な時は、こんなメンバーが揃いお喋りしたりしていた。
ちなみに僕ら以外はみんなイタリア人だ。
日本がバブル期の70年代80年代、日本人の購買力、それは凄まじいものだったらしく、多くの人達がそのビジネスに乗っかった。
ここに集う彼らは、その時代の生き残りのようでもあった。
そんな手慣れた彼らにとってすれば、まさに、カモを探す狼のようでもあった。
僕ら旅行客は、観光地に行きワイワイと楽しく舞い上がるが、その裏では僕らはしっかりとその道のプロ達に見られているのであった。
まずは添乗員さんを探す!
少し話が脱線したが、しかしコロッセオにおいては、彼らの狙いは個人客ではない。
そう、団体客だ。
その団体客を得るにはどうするか?
それがグループの責任者である添乗員さんに営業するのだった。
それは僕ら写真屋さんとて同じだった。
なので、まずグループがコロッセオにやってきた時点で、僕らは添乗員さんの姿を探す。
それらは大抵グループの後ろを一人で歩いていたり、スーツを着ていたり、書類を手に持っていたり、またお客さんの中に私服で完全に混じって楽しそうに話して歩いていたりする人もいる。
どういう風な面持ちでやってくるかは、会社の特性もあるのかもしれない。
しかし、グループである以上、必ず添乗員さんがいる。
因みに、日本人と韓国人、中国人との違いは服装で分かった。
日本人は地味な色をだいたい着ている。黒か白、ベージュや紺色か灰色あたりだ。
逆に中国人はすごく派手で、原色を着ている人も多かった。特に年配の女性はわかりやすい。日本の50年前といった印象を受けた。
韓国人はその中間。流行りの服も日本の10年くらい前、しかし、中国よりかは進んでいる。
またよく言われるがその行動様式でもだいたい分かった。
日本人はやはりあまり列を乱さないし、グループに沿って動いた。
良くも悪くも、みんながまとまっていて、騒いだりしない。行儀が良かった。
営業と添乗員さん
さて、そうやって日本人を見つけ、添乗員さんを見つけて写真を撮らせてもらえないかと営業をかける。
添乗員さんも、観光地に行く度にこういった様々な人達からアプローチされ営業をかけられるので人によっては辟易している人もいた。
しかし僕らはその売り上げの一部を添乗員さんにバックしていた。
これはこの業界では当たり前のようで、それ故に、添乗員さんもお小遣い稼ぎでこういった営業に積極的に乗ってくる人もいた。
聞いた話によると、以前、腕時計が流行っていたスイスへの旅行では、その一つあたりの単価が高いおかげで、バックされるお金も高かったようだ。そっちの方が本職の給料よりも稼げたという時代もあったらしい。
つまりこのようにお互いWin-Winの関係性でもあったのだった。
ガイドさんとは
さて、添乗員さんを口説き落としたのならばまだそれで終わりでなく、僕らに限っては次に先頭を歩いているガイドさんにも交渉しなくてはならなかった。
ガイドさんはローマに住んでいる現地の人だ。もちろんそれはイタリア人だったり、現地に住んでいる日本人だったりする。
日本人ガイドなので日本語を喋り、イタリアの国家資格であるガイドの資格を持ち、それを職業としている人達だった。習得には非常に難しいと聞く。
(ガイドさんには様々な人がいて、その後個人的に仲良くなって交流が生まれる人もいた。)
ガイドさんの仕事は一日ローマ観光のガイドを請け負っていて、歴史案内だけでなく、その時間配分からコースの設定なども行なっていた。
それ故に、人によっては、写真撮影など入れて時間を取らないでほしいという人もいたり、こういった営業全般をそもそも嫌う人もいた。
そういう人は、わざと僕らから隠れるような道でコロッセオに入ってきたり、そそくさと行ってしまったりした。
実に様々で、お客さんはどんなガイドさんと当たるかでまったく違った経験をすることになるのだろうなと思った。
ちなみに、僕らはガイドさんにも写真を売り上げたら一部をバックしていた。
そしてこの仕事をやり始めて一番大変だったのが、このガイドさんの顔と名前を全員覚える、という事だった。
日本語ガイドさんは日本人のみを連れてくる。
つまり、先頭を歩くこのガイドさんの顔を覚えてしまえば、それは間違いなく日本人グループだという訳である。
また、上記したように、写真撮影はガイドさんの協力なしには得られない。
僕ら営業と個人的に良好関係を築いておくことはとても大切なことであった。
添乗員さんとは会っても月に一回だが、ガイドさんとは毎日会うことも珍しくはなかった。
仕事と営業、短時間の出会いの中でいかに接するか
僕は毎日加藤さんに徹底的にしごかれた。
前述した、添乗員さんやガイドさんとの関係の築き方。
そして営業の核となるのはやはりお客さんとの接点だ。
僕らが実際にお客さんと接するのは短い時間だし、何よりお客さんから見れば異国の地で突然現れた日本人である。
怪しい…。(笑)
しかし、いかに怪しまれずに、信頼関係を短時間で築けるか。これに限った。
加藤さんはお客さんを「笑わせろ」と言った。
加藤さんは接客中、よく冗談を言ったりしてお客さんを笑わせ笑顔にし、この突然現れた謎の写真屋に親近感を持ってもらっていた。
僕は、10代の頃からバイトを含め色々な仕事をしてきたが、こういった営業や人の前で話すというのは初めての事だった。
これは僕にとって、まったく新しい挑戦だった、故に失敗も多くした。
しかしその度に悔しい思いをし、学ぶことの多さに気付いて行った。
僕は意味を持ってこの仕事に真正面から取り組んでいったのだった。
写真配達、ローマの街を駆け巡れ!
さて、写真は撮ってそれで終わりではない。
コロッセオに16時までいると、その後は現像した写真の配達があった。
撮ってその日の内に渡さなければ、ツアー旅行はもう明日にはこの街にはいない。
ツアー旅行ほど忙しいものもないのである。
さて渡す場所はいくつかあった。
それらは夕食を取るレストラン、または自由行動後の集合場所。他にも三越やホテルまで行く事もあった。
僕と加藤さんは手分けして配達に向かった。
ローマの地図を片手に地下鉄とバスを乗り継いで行く。
だいたいツアー旅行で使われるレストランは限られているので、一軒のレストランに何団体もの日本人グループがいたりして、そこで一気に渡せたりする事も多かった。
そういうレストランはカンツォーネ(イタリア民謡)のショーがあったりしてちょっと面白い。陽気な日本人のおじさん達は一緒に歌ったりしている♪
そういった場所がローマの色々な場所にあった。
また三越は、お客が現地で迷子になったりした時の寺小屋的存在でもあり、そこを頼りにしている添乗員さんも多くいた。
そしてホテルだが、これは遠くにある事が多かったのでその前のどこかで受け渡せるようにしたかった。
特に安いツアーだと、そのホテルは郊外の遠い地にあったりして行くのに苦労した。
それでも、仕事でローマ中の色々なところへと行けたのには面白かった。
古き街並みは日本のそれとはまったく異なり、オレンジ色の街灯がその情緒を色濃く醸し出した。
単純に美しい。ここにいると日々感性が磨かれているようでもあった。
さらに驚いたのはその建物で、ローマで築100年であれば新しいと言われ、街中には平気で500年、600年前、時に1000年前と言われるものまでが建っていて人が未だに普通に住んでいる。
ただ、そういった古い建物は唯一の難点としてエレベーターがないので、住む苦労ももちろんありそうだったが。
ロマンライフ
僕は仕事にも慣れ、また加藤さんとも良いコンビで動けるようになってくるのにそう時間はかからなかった。
もともと人が好きで、話すのも好きだったのもあるだろう。
営業は常に向上の余地があるが、僕のやる気と前向きな姿勢は大きく評価され、加藤さんや社長の一柳さんからの信頼を得ていった。
一柳さんは、事あるごとに僕らを食事にも連れ出してくれた。
美味しいパスタのお店や、ローマの郷土料理のお店などは、長年現地に住んでいる人ならではの知るところだが、しかし僕らは中華にもよく行った^^
やはり、母国と馴染みある料理が結局は食べたくなるものである!
一柳さんは食卓を囲む度に、毎回今後の夢を聞かせてくれたり、また彼の人生哲学を語ってくれた。
それは説教臭くもあるが、まだ若かりし自分にとってはそれは貴重な学びでもあり、また海外経験豊富なその言葉は興味深くもあった。
こうして、僕の新しい生活は順調に過ぎていったのであった。
【イタリアとの出合い6へ続く】
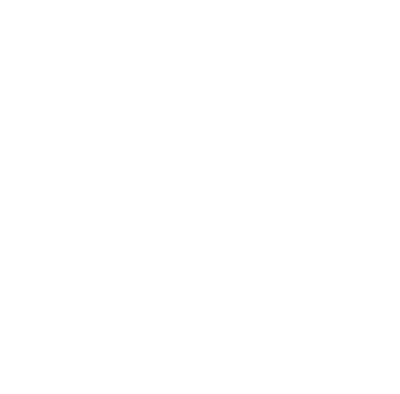 World Performing Blog!
World Performing Blog! 





